宇宙人目撃情報の歴史と信憑性
人類が夜空を見上げ始めた時から、私たちは「我々は宇宙で孤独なのか」という根源的な問いを抱いてきました。現代においても、この疑問への答えを追い求める中で、宇宙人やUFOの目撃情報は絶えることなく報告され続けています。これらの目撃情報は単なる思い込みなのか、それとも何か真実を映し出しているのでしょうか。
ロズウェル事件の真相
1947年7月、ニューメキシコ州ロズウェル近郊で発生した「何か」の墜落事故は、現代UFO神話の原点とも言える出来事です。当初、ロズウェル陸軍航空基地の広報官は「空飛ぶ円盤を回収した」との声明を出しましたが、わずか数時間後にはこれを撤回し、「気象観測用バルーン」の残骸だったと訂正しました。この急激な声明変更が、数十年にわたる陰謀論の火種となりました。
実際、米軍が1994年に公表した公式報告書では、墜落物体は秘密軍事プロジェクト「モグル計画」の高高度気球だったと説明されていますが、これに納得しない研究者や目撃者も多数存在します。元基地職員の一部は、生涯をかけて「異星の乗り物と乗員を見た」と主張し続けました。
特筆すべきは、当時の社会背景です。冷戦初期、核開発競争の最中において、未知の飛行物体に関する情報が国家安全保障上の懸念事項だったことは想像に難くありません。このことが情報の混乱や意図的な操作を引き起こした可能性も指摘されています。
世界各国の主要な目撃事例とパターン

ロズウェル以降も、世界中で報告される目撃情報には興味深いパターンが見られます。
主な目撃事例の特徴:
- 円盤状・三角形・葉巻状の形状
- 不可能と思われる急旋回や加速
- 音もなく高速で移動する能力
- 電子機器への干渉
- 特定の地域や軍事施設周辺での頻発
特に注目すべきは、1989年から1990年にかけてベルギーで発生した「ベルギー・ウェーブ」と呼ばれる現象です。一晩で数千人もの市民が巨大な三角形の飛行物体を目撃し、ベルギー空軍のF-16戦闘機がこれを追跡する事態となりました。レーダーにも捉えられたこの物体は、物理法則を無視するかのような動きを見せたと報告されています。
政府機関による調査記録
各国政府は公式にUFO調査プログラムを実施してきました。米国の「ブルーブック計画」(1952-1969)、フランスの「GEPAN/SEPRA」(1977-)、英国の「UFOデスク」(1950-2009)などが代表例です。これらの調査では、多くの目撃が誤認や自然現象として説明される一方で、「未確認」のままとされる事例も少なくありません。
2020年に米国防総省が「未確認航空現象タスクフォース(UAPTF)」を設立し、現役パイロットのUAP(Unidentified Aerial Phenomena:未確認航空現象)報告を公式に収集・分析しているという事実は、この問題が今なお真剣に検討されていることを示しています。
目撃証言の共通点と科学的検証
多くの目撃証言に共通する要素として、従来の航空技術では説明できない動きや物理特性があります。特に次の点は科学的に興味深いとされています:
| 特性 | 従来技術との比較 | 科学的検証の難しさ |
|---|---|---|
| 瞬時加速 | 数百Gの加速度は人間パイロットが耐えられない | 映像証拠だけでは距離感の錯覚の可能性がある |
| 超音速移動時の衝撃波なし | 現代の航空機は超音速で必ず衝撃波を生じる | 目撃者証言と計測機器の不一致 |
| 水中/空中の自由移動 | 既存の乗り物では不可能 | 検証可能な物的証拠の不足 |
こうした特性を科学的に検証するには、多角的なデータ収集が不可欠です。しかし、現象の予測不可能性と一過性、さらに公的研究への資金不足や社会的タブーが、体系的な研究を困難にしてきました。
一方で、科学者や研究者の間では、これらの現象を単なる誤認や錯覚として片付けるのではなく、未知の自然現象や先進技術の可能性として、より開かれた科学的態度で調査する必要性が認識されつつあります。謎を解明するには、先入観なしに証拠を検証する姿勢が求められているのです。
政府の機密解除文書からわかること
近年、世界各国の政府が機密解除した文書の中には、未確認飛行物体(UFO)に関する驚くべき情報が含まれています。これらの公式記録は、長年「陰謀論」として片付けられてきた現象に対して、政府機関が真剣に調査・分析していた事実を明らかにしています。
米国防総省のUFO映像公開の意味
2020年4月、米国防総省は公式にF/A-18スーパーホーネット戦闘機のパイロットが撮影した三つのUFO映像を公開しました。「FLIR」「GIMBAL」「GOFAST」と名付けられたこれらの映像は、赤外線カメラで捉えられた高速で動く物体を映しています。特に注目すべきは、これらが「未確認航空現象(UAP)」として公式に認められたことです。
国防総省の報道官は「これらの現象が何であるかを特定することはできなかった」と述べ、同時に「未確認航空現象に関する事実関係の理解を深めるため」という目的を掲げています。この公式発表は、政府が未知の飛行物体を単なる誤認や自然現象として片付けるのではなく、安全保障上の潜在的脅威として真剣に捉えていることを示唆しています。
さらに重要なのは、これらの映像を撮影したパイロットたちの証言です。元米海軍パイロットのデイヴィッド・フレイヴォー中佐は、2004年に目撃した物体について「表面は滑らかで、40フィート(約12メートル)ほどの長さで、楕円形をしていた」と証言しています。彼らの訓練された目が捉えた観察は、単なる錯覚や誤認として簡単に退けられるものではありません。
各国の軍事機関が認めた未確認飛行物体
米国だけでなく、世界各国の政府も同様の現象を記録しています。

フランス:フランス国立宇宙研究センター(CNES)は1977年から「GEPAN」(後に「GEIPAN」に改称)というUFO調査部門を公式に設置し、今日まで活動を続けています。その調査結果のうち、約22%の事例が「未説明」のままとされています。
イギリス:英国防省が2008年に公開した「UK UFO Files」には、1950年代から2009年までに記録された数千件の報告が含まれています。特に注目すべきは、1993年に複数の軍事基地で観測された「コスフォード事件」で、レーダーにも捉えられた三角形の物体が低空で無音飛行する様子が記録されています。
ブラジル:1986年、ブラジル空軍の戦闘機が複数のUFOを追跡した「公式UFO夜」として知られる事件では、レーダーと目視の両方で確認された20機以上の物体が、戦闘機の最高速度を超える速度で飛行したと報告されています。
ロシア:旧ソ連時代から現在まで、ロシアも公式にUFO現象を研究しており、特に核施設周辺での目撃が多数記録されています。
これらの各国政府文書に共通するのは、軍事関係者による観測、複数の信頼できる証人、レーダーなどの計測機器による裏付けという三要素を満たす事例が存在することです。
元政府関係者の証言
機密解除文書と並んで重要なのが、元政府関係者や軍人による証言です。
2010年に開催された「市民公聴会」では、元米空軍将校のロバート・サラス氏が、1967年にモンタナ州の核ミサイル基地上空に出現したUFOにより、複数の核ミサイルが突如として作動不能になった事件について証言しました。同様の事例はソ連の基地でも報告されており、UFOと核施設の関連性を示唆しています。
元カナダ国防大臣のポール・ヘルヤー氏は、2005年以降、複数の宇宙人種がすでに地球を訪れているという信念を公に表明し、各国政府にUFO情報の公開を求める活動を行っています。
専門家証言の信頼性評価基準:
- 専門的訓練と経験の有無
- 証言の一貫性と詳細さ
- 他の証人や証拠との整合性
- 個人的利益(本や講演料など)との関係
文書から読み取れる技術的特徴
機密解除文書から浮かび上がるUFOの技術的特徴は、現代科学の理解を超えるものが多く含まれています。
| 報告される特性 | 文書での言及頻度 | 現代技術との比較 |
|---|---|---|
| 瞬時加速・減速 | 非常に高い | 既知の推進システムでは不可能 |
| 直角転回 | 高い | 慣性の法則に反する |
| 電磁干渉 | 中程度 | 強力な電磁場の発生を示唆 |
| 反重力効果 | 低~中 | 理論的に可能だが実現していない |
| 透明化現象 | 低い | 現代の光学迷彩技術を超越 |
こうした特性は、単一の自然現象や既知の航空技術では説明が困難です。特に、瞬時加速や直角転回は、搭乗者(もしいるとすれば)に致命的なGフォースをかけるはずですが、それでも飛行を続けるという矛盾が存在します。
これらの公開文書が示すのは、少なくとも一部のUFO現象が、単なる誤認や自然現象ではなく、私たちの現在の科学的理解を超えた何かである可能性です。それが地球外起源であるかどうかは別として、これらの現象は真剣な科学的探究に値するものと言えるでしょう。
科学者たちの見解と研究の現状
UFOや地球外知的生命体の可能性に対する科学者たちの姿勢は、長い間「笑いごと」として片付けられる風潮がありました。しかし近年、天文学や宇宙生物学の進展により、この問題に対する科学的アプローチが徐々に市民権を得つつあります。まじめな研究者たちは、感情的な信念や否定ではなく、証拠に基づいた議論を展開しています。
異星知的生命体の存在可能性
宇宙における生命、特に知的生命体の存在確率を考える上で最も重要な進展は、系外惑星の発見です。1995年に最初の系外惑星が確認されて以来、現在では5,000個以上の惑星が発見されており、その中には「ハビタブルゾーン」(生命が存在できる可能性のある領域)に位置する地球型惑星も含まれています。
NASA宇宙生物学研究所の最新の推定によれば、銀河系内だけでも居住可能な惑星は数十億個存在する可能性があります。この膨大な数字は、生命が地球だけに限定されているという考えに科学的な疑問を投げかけています。
生命発生の条件:
- 液体の水の存在
- 炭素などの有機物質
- エネルギー源
- 適切な温度と圧力
- 有害な放射線からの保護
これらの条件を満たす惑星が多数存在することが明らかになりつつある現在、カリフォルニア大学バークレー校の天文学者フランク・ドレイク博士が1961年に提唱した「ドレイク方程式」が再評価されています。この方程式は銀河系内の交信可能な文明数を推定するもので、最新のパラメーターを適用すると、銀河系内には数十から数万の知的文明が存在する可能性があります。

しかし、生命の発生と進化、特に知性の発達における確率は依然として大きな未知数です。ハーバード大学の天文学者アヴィ・ローブ教授は「宇宙の広大さを考えると、地球外知的生命体の存在を否定するよりも、その可能性を真剣に探究すべきだ」と主張しています。
現代物理学からみた宇宙間移動の課題
仮に知的生命体が他の恒星系に存在するとして、彼らが地球を訪れることは物理的に可能なのでしょうか。最大の障壁となるのは、光速という宇宙の速度制限と、恒星間の途方もない距離です。
最も近い恒星系であるケンタウルス座アルファ星までの距離は約4.3光年(約41兆キロメートル)あります。現在の人類の最速宇宙船でも、そこに到達するには数万年かかるでしょう。
しかし、理論物理学の分野では、光速制限を「回避」する概念的可能性がいくつか提案されています:
| 理論的概念 | 基本原理 | 現実的課題 |
|---|---|---|
| ワームホール | 時空を折り曲げて遠距離を接続 | 負のエネルギーが必要で安定性に問題 |
| アルクビエレ・ワープドライブ | 周囲の時空を圧縮・拡張 | 莫大なエネルギーと未知の物質が必要 |
| 量子エンタングルメント | 量子的に結合した粒子間の瞬時の相互作用 | 情報転送への応用は未解決 |
カリフォルニア工科大学の理論物理学者キップ・ソーン博士は「ワームホールの理論的可能性は排除できないが、実現には我々の知らない物理法則の発見が必要だろう」と述べています。
重要なのは、人類の科学技術の歴史はわずか数百年に過ぎず、数千年や数百万年進んだ文明の技術的能力を予測することはほぼ不可能だという点です。100年前の人間にとって、今日のスマートフォンや量子コンピューターは「魔法」のように見えたでしょう。
SETI計画の成果と限界
地球外知的生命体の探索(Search for Extra-Terrestrial Intelligence: SETI)は、1960年代から電波望遠鏡を使って宇宙からの人工的な信号を探す取り組みを続けてきました。これまでに確認された有力な信号としては、1977年の「ワオ!信号」が知られていますが、その後の再確認はできていません。
SETIの限界としては以下の点が挙げられます:
- 電波通信が普遍的なコミュニケーション手段とは限らない
- 宇宙の広大さに比べて観測できる範囲が極めて限定的
- 短期間の観測では、断続的な信号を見逃す可能性
- 高度な暗号化された信号は、ノイズと区別できない可能性
2015年に開始された「ブレークスルー・リッスン」プロジェクトでは、100万の恒星系を対象に、これまでで最も広範囲かつ高感度な探索が行われていますが、現在までに確認された外部知的生命体からの信号はありません。
アストロバイオロジーの最新知見
アストロバイオロジー(宇宙生物学)は、宇宙における生命の起源、進化、分布、未来を研究する学際的分野です。近年の重要な発見には以下のものがあります:
- 火星の土壌から有機分子の検出
- 木星の衛星エウロパとタイタンに液体の海の存在確認
- 彗星や小惑星から生命の構成要素となる複雑な有機物の発見
- 極限環境下で生存する地球上の「エクストリームフィル」微生物の研究
特に注目すべきは、2020年にJAMSのウェブ宇宙望遠鏡によって系外惑星の大気組成を分析する能力が向上したことで、将来的に生命の痕跡(バイオシグネチャー)を検出できる可能性が高まっています。
こうした科学的進展は、UFO現象が本当に地球外知的生命体によるものかどうかを直接証明するものではありませんが、宇宙における生命の可能性についての私たちの理解を深め、議論の土台を科学的なものへと変えつつあります。
最終的に、科学者たちは「可能性は排除できないが、証拠がなければ結論を出せない」という慎重な立場を取りつつも、未知の現象に対する好奇心と探究心を失わないことが重要だと強調しています。
隠蔽説の根拠と限界
UFO現象や地球外生命体に関する政府の隠蔽(カバーアップ)は、長年にわたり最も強力な陰謀論の一つとして浸透してきました。「政府は真実を知っているが、公表していない」という主張は、どこまで信頼できるのでしょうか。この説の根拠となる事実と、その限界について検証していきましょう。
政府による情報管理の実態
情報管理と国家機密は、現代国家の機能として正当な側面を持ちます。特に安全保障に関わる情報は、厳格に管理されるのが通例です。UFO現象に関しても、冷戦期には軍事偵察技術との混同を避けるため、情報操作が行われていた事例が文書で確認されています。
1950年代、米空軍の「ブルーブック計画」の内部文書では、公式見解と異なる評価が記されていたことが機密解除後に明らかになりました。また、CIAの内部メモでは「国家安全保障上の理由から、一般大衆のUFOへの関心を減少させる必要がある」と明記されていました。
このような情報管理の実態は、「隠蔽」と呼べる側面があることは否定できません。しかし、これが必ずしも「異星人の存在を隠している」ことを意味するわけではありません。むしろ、多くの場合、秘密にされていたのは軍事技術や諜報活動に関連する事実でした。

政府による情報統制の具体例:
- 1947年:ロズウェル事件後の急な公式発表の変更
- 1952年:ワシントンDC上空UFO目撃時の情報制限
- 1966年:ミシガン州で多数の目撃があった「スワンプガス」説明への疑問
- 1975年~1976年:軍事基地上空でのUFO目撃に関する軍の矛盾した説明
- 1980年:レンドルシャム・フォレスト事件の関連記録の「紛失」
特に注目すべきは、2017年に明らかになった米国防総省の極秘UFO調査プログラム「先進航空脅威特定プログラム(AATIP)」の存在です。この2007年から少なくとも2012年まで続いたプログラムは、年間2,200万ドルの予算で運営されていましたが、その存在自体が長年公表されていませんでした。
エリア51とその周辺の謎
ネバダ州の砂漠地帯に位置する極秘軍事施設「エリア51」は、UFO隠蔽説の中心的存在となっています。この施設の存在自体、米政府は長年認めず、2013年になってようやく公式文書で言及されました。
エリア51の主な目的は、実際には最先端軍用機の開発・テスト基地であることが知られています。U-2偵察機やSR-71ブラックバード、F-117ナイトホークなどの秘密裏の開発が行われ、これらの未知の航空機のテスト飛行が多くのUFO目撃に繋がったことは間違いありません。
しかし、同施設を取り巻く異常な警備レベルと「立ち入れば射殺する」警告、周辺での奇妙な光や物体の目撃は、単なる航空機開発だけでは説明しきれない部分があると主張する声も根強くあります。
元施設職員ボブ・ラザールの証言は最も有名な事例です。彼は1989年、エリア51の「S-4」と呼ばれる施設で異星の航空機を研究していたと主張し、その推進システムなどの詳細を公表しました。彼の証言は多くの矛盾を含むとされる一方で、後に事実と確認された情報も含んでいた点で議論を呼んでいます。
陰謀論が広がる社会的背景
UFO隠蔽説を含む陰謀論が社会に浸透する背景には、複数の心理的・社会的要因が存在します。
陰謀論が受け入れられやすい条件:
- 政府や権威に対する不信感の高まり
- 複雑な問題に対するシンプルな説明への渇望
- インターネットによる情報拡散と「エコーチェンバー」の形成
- メディアによる扇情的な取り上げ方
- 実際の政府の秘密工作の歴史(MKウルトラ計画など)
社会心理学者のロブ・ブラザートン博士は「陰謀論は不確実性に対処するための人間の認知メカニズムだ」と説明しています。特に、大規模な社会変革期や危機的状況では、隠れた力によって世界が操作されているという説明が魅力的に映りやすくなります。
一方で、すべての陰謀論を単なる妄想として切り捨てることも危険です。歴史的に見れば、当初は「陰謀論」と呼ばれた主張が後に事実として証明された例も存在します。ウォーターゲート事件やCIAの極秘人体実験などがその一例です。
情報開示を求める市民運動とその成果
近年、UFO情報の公開を求める市民運動は、一定の成果を上げています。「情報自由法(FOIA)」を活用した請求により、数多くの政府文書が機密解除されてきました。
市民活動の主な成果:
- 1978年:CIAのUFO関連文書の公開(約900ページ)
- 1997年:米空軍の「ブルーブック計画」文書の完全公開
- 2007年:フランス国立宇宙研究センターによるUFO関連文書の公開
- 2008年:英国防省の「UFOファイル」の段階的公開開始
- 2020年:米国防総省による公式UFO映像の認証と公開
特に注目すべきは、2020年に成立した「コロナウイルス救済・対応法」に盛り込まれた条項で、米情報機関に対し「未確認航空現象」に関する情報を180日以内に議会に報告することが義務付けられたことです。この成果は、退役軍人や元政府関係者を含む「情報開示を求める会」などの団体の長年の働きかけによるものです。
しかし、情報開示には依然として大きな壁が存在します。安全保障上の理由による公開拒否や、重要部分の墨塗り、そもそも記録が存在しないケースなど、完全な透明性の実現は困難を極めています。
UFO隠蔽説の核心には、「証明不可能性」という本質的なジレンマがあります。政府が「すべての情報を公開した」と主張しても、「真の秘密はさらに隠されている」と考えることは常に可能だからです。
真実を追求するには、盲目的な信念や全面的な否定ではなく、証拠に基づく批判的思考と、未知の現象に対する謙虚さの両方が求められているのです。
科学的批判精神と謎の解明
UFO現象や宇宙人に関する議論において最も重要なのは、科学的批判精神を持ちながらも、未知の現象に対する好奇心と開かれた姿勢を失わないことです。この最終章では、UFO現象に対する合理的なアプローチと、謎解明への道筋について考察します。
UFO現象の合理的説明

UFO目撃の多くは、自然現象や人工物の誤認によって説明できることが、これまでの研究で明らかになっています。専門家による慎重な分析により、「未確認」とされていた事例の約90〜95%は、以下のような既知の現象として説明されています。
UFOと誤認されやすい現象:
| 現象 | 特徴 | 目撃例 |
|---|---|---|
| 金星・木星などの惑星 | 大気条件により明滅・色変化 | 夕暮れ時の低空での明るい光 |
| 気象観測気球・研究用気球 | 高高度での反射、特異な動き | 白い円盤状の浮遊物体 |
| 軍用機・試験機 | 高速移動、通常とは異なる形状 | 三角形の黒い物体 |
| ボールライトニング | 電気的な浮遊球体、不規則な動き | 明るく脈動する球体 |
| レンズ雲 | 円盤状の雲形成、静止して見える | 山の上や高空の円盤状物体 |
| 気象逆転層による光の屈折 | 遠方の光源が浮いて見える | 動かない複数の光点 |
これらの説明は、単にUFOの存在を否定するためではなく、科学的手法による現象理解の一環です。実際、科学的に説明できる事例を除外することで、本当に謎の残る現象に焦点を絞ることができます。
天文学者のカール・セーガンは「並外れた主張には、並外れた証拠が必要だ」という有名な言葉を残しました。地球外知的生命体の存在は、人類の世界観を根本から変える可能性のある「並外れた主張」であり、それに見合った確固たる証拠が求められるのは当然と言えるでしょう。
誤認と錯覚のメカニズム
UFO目撃において誤認が生じる理由を理解することは、現象の科学的理解において重要です。人間の認知システムには、以下のような特徴があります。
目撃証言の信頼性に影響する要因:
- 遠方の物体の距離と大きさの見積もりの困難さ
- 予期せぬ現象に対する脳の「意味付け」傾向
- 眼球運動による光源の見かけの動きの錯覚
- ストレスや興奮状態での記憶の変容
- 事後的な情報による記憶の汚染
- 先入観による知覚の歪み
心理学研究では、同じ現象を目撃しても、人によって全く異なる証言をすることが実証されています。これは目撃者の不誠実さによるものではなく、人間の知覚・記憶システムの本質的な特性です。
特に興味深いのは「フラッシュメモリー」と呼ばれる現象で、強い感情を伴う出来事の記憶は鮮明に感じられるにもかかわらず、実際には通常の記憶と同様、あるいはそれ以上に変容しやすいことが知られています。
心理学者のエリザベス・ロフタス博士は「UFO目撃者が虚偽の証言をしているとは限らない。彼らは自分が見たと信じている内容を正直に語っているのだ」と指摘しています。
現代技術による検証方法
テクノロジーの進歩により、UFO現象の検証方法は大きく進化しています。以下のような技術が現在活用されています:
- 高解像度カメラネットワーク:24時間体制で空を監視するカメラネットワークが世界各地に設置されています。「ガリラオプロジェクト」などの取り組みでは、複数の高性能カメラによる同時観測と三角測量で、物体の正確な高度・速度・サイズを計測できます。
- マルチスペクトル分析:可視光だけでなく、赤外線・紫外線・電波など複数の波長での観測により、物体の物理的特性をより詳細に分析できます。
- レーダー・赤外線・磁場センサーの組み合わせ:複数の異なる検出方法を組み合わせることで、単一の観測手段では捉えられない現象の全体像を把握できるようになっています。
- AIと機械学習:膨大な観測データから異常パターンを検出するAIシステムの開発が進んでいます。ハーバード大学のアヴィ・ローブ教授率いる「ガリラオプロジェクト」では、AIを活用した天体観測データの分析が行われています。
これらの技術的アプローチは、主観的な目撃証言への依存から、客観的で再現可能なデータ収集へとUFO研究を変革しつつあります。
市民科学の可能性と限界
インターネットの普及と低コスト高性能機器の登場により、一般市民による科学的調査「市民科学」の可能性が広がっています。UFO現象の研究においても、訓練された一般市民による観測ネットワークが貢献しています。
市民科学のメリット:
- 広範囲での常時観測体制
- 多様な視点と創造的アプローチ
- 専門家では見落とされがちな現象への注目
- 科学的リテラシーの向上

一方で、市民科学には以下のような限界も存在します:
市民科学の限界:
- 専門的知識や訓練の不足
- 観測機器の精度・性能の制約
- データ解釈における先入観の影響
- 一貫した方法論の確立と維持の難しさ
これらの限界を克服するためには、専門研究機関と市民科学者の協力関係が不可欠です。米国のUFO報告システム「MUFON」や、科学者主導の「UFODATA」プロジェクトなどは、市民からの報告を科学的に分析するプラットフォームを提供しています。
最終的に、UFO現象の真相解明には、固定観念にとらわれない柔軟な思考と、厳密な科学的方法論の両立が求められます。懐疑主義者が「すべてを否定」し、信奉者が「すべてを信じる」という両極端を避け、複雑な現象に対する総合的な理解を目指す姿勢が重要です。
科学の歴史は、「不可能」とされていたことが後に可能になった例に満ちています。UFO現象についても、今日の「不可解」な事例が、明日の科学的発見につながる可能性は十分にあります。重要なのは、好奇心と批判的思考を手放さず、証拠に基づいて一歩一歩真実に迫る姿勢を保つことではないでしょうか。
ピックアップ記事

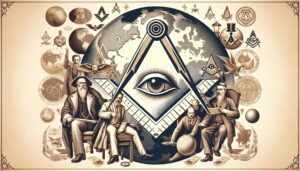



コメント