1. 山口組とCIAの噂:歴史的背景と真相
日本の裏社会と米国情報機関の関係性は、長年にわたり様々な憶測を呼んできた謎めいたトピックです。山口組という日本最大の暴力団とCIA(アメリカ中央情報局)の間に何らかの繋がりがあったのではないかという噂は、戦後日本の複雑な政治情勢と国際関係の中で生まれました。しかし、どこまでが事実で、どこからが都市伝説なのでしょうか?
1-1. 戦後日本における米国の影響力と裏社会
第二次世界大戦後、日本はアメリカの占領下に置かれ、GHQ(連合国軍総司令部)による統治が始まりました。この時期、日本社会の再建と民主化が進められる一方で、混乱した社会情勢の中で闇市場が発達し、ヤクザ組織が力をつけていきました。
占領期の特殊な環境
- 物資不足による闇市場の拡大
- 帰還兵の社会復帰問題
- 政治的空白地帯の出現
- 旧軍人や右翼団体の再編
こうした背景の中、アメリカ側は日本の治安維持と反共産主義政策の一環として、皮肉にも一部の右翼団体やヤクザ組織を暗黙の「協力者」として利用したとされています。特に注目すべきは1949年から1952年にかけての時期で、冷戦の緊張が高まる中、CIAは日本国内での共産主義の拡大を阻止するために様々な工作活動を行っていたことが、後の文書公開で明らかになっています。
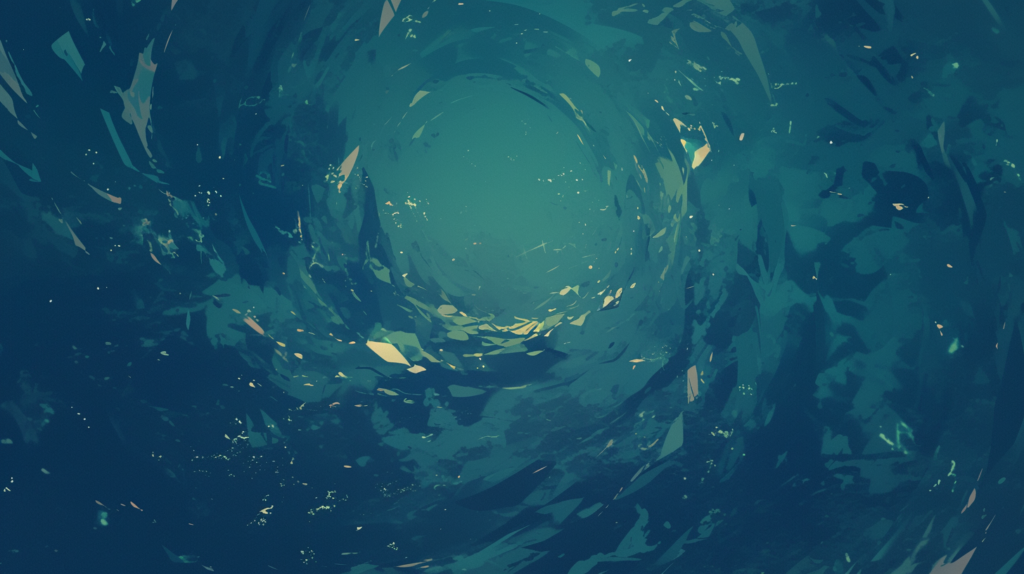
山口組が現在の形で勢力を拡大し始めたのもこの時期と重なります。3代目山口組組長・田岡一雄の下で、神戸を拠点に組織は急速に発展しました。ただし、田岡一雄自身がCIAと直接的な関係を持っていたという確固たる証拠は見つかっていません。
1-2. 情報機関と組織犯罪の複雑な関係性
情報機関が特定の目的のために組織犯罪グループを利用するという構図は、世界的に見れば珍しいことではありません。20世紀の歴史を振り返ると、以下のような事例が確認されています:
| 時期 | 地域 | 情報機関 | 犯罪組織 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 1940年代 | シチリア | OSS(CIAの前身) | シチリアマフィア | 連合軍上陸作戦支援 |
| 1960年代 | キューバ | CIA | アメリカマフィア | カストロ暗殺計画 |
| 1980年代 | 中南米 | CIA | 麻薬カルテル | 反共ゲリラへの資金提供 |
日本の場合、公式記録に残る直接的な協力関係の証拠は限られていますが、「相互不干渉」や「黙認」という形での関係があった可能性は否定できません。特に注目すべきは、1950年代から60年代にかけて、日本の右翼団体と山口組の一部が、労働争議の抑え込みや左翼勢力への対抗という点で、結果的にアメリカの冷戦戦略と利害が一致していた点です。
「CIAが山口組を直接操っていた」という陰謀論的な見方は誇張でしょうが、情報収集や特定の政治目的のために間接的な関係があった可能性は、研究者の間でも指摘されています。
1-3. 公式記録と証言:どこまでが事実か
1-3-1. 元情報部員の告白
2000年代に入り、元CIA職員や日米の元情報関係者からの証言が徐々に明らかになってきました。特に注目すべきは、1995年に出版された元CIA日本担当官のビル・プリット(仮名)の回顧録です。彼は著書の中で、「1950年代から60年代にかけて、特定のヤクザ組織の幹部と非公式な接触があった」と証言しています。
ただし、こうした証言の信頼性には常に疑問が付きまとうことを忘れてはなりません。元情報部員の回顧録には、しばしば誇張や選択的な記憶が含まれる可能性があります。また、情報機関の元職員が公開できる情報には法的・制度的制限があることも考慮すべきでしょう。
1-3-2. 文書公開から見えるもの
アメリカの情報公開法(FOIA)に基づいて機密解除された文書からは、CIAが日本国内で様々な工作活動を行っていたことは明らかになっています。例えば、以下のような活動が確認されています:
- 自由民主党への資金提供
- 労働組合への浸透工作
- 学生運動の監視
- メディア操作
しかし、山口組との直接的な関係を示す公式文書は、現時点では発見されていません。ただ、「ナショナルセキュリティ」を理由に、今なお多くの文書が機密指定されたままであることも事実です。この謎めいた関係の全貌は、将来更なる文書公開があって初めて明らかになるのかもしれません。
2. 冷戦期の日本:CIAの対日工作と山口組の台頭
冷戦が本格化した1950年代から1980年代にかけて、日本は東西対立の最前線ではないものの、アジアにおける重要な地政学的位置を占めていました。この時期、CIAの対日工作と山口組の勢力拡大が同時進行で進んだことは、単なる偶然でしょうか、それとも何らかの因果関係があったのでしょうか。
2-1. 共産主義への対抗とヤクザの利用価値
1950年代、朝鮮戦争の勃発とともに、アメリカにとって日本の政治的安定は最優先事項となりました。当時、日本共産党の影響力拡大や労働運動の活発化は、アメリカにとって「赤い脅威」と映っていたのです。
CIAの対日工作の主な目標
- 日本共産党の弱体化
- 労働組合の分断
- 保守政権の維持支援
- 反米感情の抑制
こうした目標を達成するため、CIAはあらゆる手段を模索していました。実際、1953年にアレン・ダレスCIA長官が来日した際、日本の右翼勢力や保守政治家との接触があったことが、後の調査で明らかになっています。

この文脈で注目すべきは、山口組を含むヤクザ組織が持つ「反共」的な政治姿勢です。戦前から右翼的思想と結びつきの強かったヤクザ組織は、左翼勢力への対抗勢力として、結果的にアメリカの冷戦戦略と利害が一致する場面がありました。
特に1960年の安保闘争の際には、右翼団体と連携したヤクザ組織の一部が、デモ隊への妨害行動を行ったという証言もあります。これらの行動がCIAの指示によるものだったという直接的証拠はありませんが、「黙認」または「間接的支援」があった可能性は否定できません。
2-2. 政治的安定のための「必要悪」という見方
冷戦期のアメリカ外交政策において、「敵の敵は味方」という考え方は珍しくありませんでした。共産主義という「より大きな敵」に対抗するため、道徳的に問題のある集団や個人と協力することも厭わない姿勢が見られました。
山口組を含む日本の暴力団は、次のような点で「必要悪」として機能していた可能性があります:
- 社会不安の抑制装置:労働争議や学生運動が激化した際、暴力団は実力行使による鎮静化の役割を果たすことがありました。
- 情報源としての価値:裏社会に精通するヤクザは、公式ルートでは得られない情報を提供できる立場にありました。
- 非公式外交チャネル:表向きの外交では対応できない問題を、裏チャネルで解決する役割を担うことがありました。
1972年に発表された「田中角栄メモランダム」(真偽については議論がある)では、山口組と政財界との繋がりが指摘されており、そこにはアメリカの情報機関との接触についても言及があったとされています。ただし、この文書の真正性は確認されておらず、都市伝説の域を出ません。
2-3. 経済成長と裏社会の変容
2-3-1. バブル経済と組織犯罪の拡大
1970年代から80年代にかけて、日本は高度経済成長からバブル経済へと移行しました。この経済的繁栄の影で、山口組は組織としての性格を大きく変化させていきます。
バブル期の山口組ビジネス
- 不動産投資と地上げ
- 建設業への進出
- 金融・投資事業
- 歓楽街の管理
- 企業舎弟制度の拡大
特に注目すべきは、この時期に山口組が「経済ヤクザ」としての性格を強め、表社会との境界線が曖昧になっていった点です。高度に組織化され、企業的手法を取り入れた山口組は、CIAにとっても従来の「単なる犯罪組織」というイメージから脱し、より複雑な評価の対象となっていきました。
1980年代後半、アメリカ財務省やFBIは、日本のヤクザ組織による米国不動産への投資や資金洗浄に注目し始めます。冷戦末期になると、CIAの関心も「共産主義の脅威」から「国際組織犯罪」へとシフトしていきました。
2-3-2. 国際的なネットワークの形成
バブル経済が最盛期を迎えた1980年代後半、山口組は国際的なネットワークを構築し始めました。特に以下の地域との繋がりが強化されています:
- 韓国・台湾(地理的近接性)
- 香港・マカオ(カジノ産業との関連)
- ハワイ・カリフォルニア(日系社会との繋がり)
- ラスベガス(ギャンブル産業)
この国際化は、CIAや他の米国機関にとって新たな監視対象となりました。冷戦構造が揺らぎ始めたこの時期、アメリカの情報機関にとっての優先順位も変化し、「反共の同盟者」としての価値よりも「国際犯罪組織」としての脅威が強調されるようになっていきます。
1992年、米国議会で初めて「日本のヤクザ問題」に関する公聴会が開かれたことは、こうした認識の変化を象徴する出来事でした。冷戦の終結とともに、かつての「暗黙の了解」は崩れ、山口組とCIAの関係も新たな局面を迎えることになったのです。
3. 現代における山口組とアメリカの情報機関の関係
冷戦終結後の1990年代から現在に至るまで、山口組とアメリカの情報機関の関係性は大きく変化しました。かつての「暗黙の協力」から「監視対象」へと転換し、国際的な法執行協力の枠組みの中で新たな関係が構築されています。この変化は世界情勢の変動と国際犯罪の性質の変化を反映したものといえるでしょう。
3-1. テロとの戦いと国際犯罪組織への監視強化
2001年の9.11テロ事件は、アメリカの情報機関の優先事項を根本的に変えました。テロリズムとの闘いが最優先課題となる中で、国際犯罪組織とテロ組織の潜在的な繋がりに対する警戒も強まりました。
テロ対策としての組織犯罪監視
- 資金調達ルートの追跡
- 武器・爆発物の調達経路の監視
- 偽造文書ネットワークの摘発
- マネーロンダリングの取締り強化
この文脈で、日本の暴力団もアメリカの情報機関からは潜在的なリスク要因として再評価されました。特に北朝鮮との繋がりが指摘されてきた一部のヤクザ組織は、核・ミサイル開発に関連する物資の密輸や資金調達に関与している可能性から、CIA等の監視対象となっています。

2011年には、アメリカ財務省が山口組の幹部を含む複数のヤクザ関係者を「特別指定国際犯罪組織」(SDNTK)に指定し、資産凍結や取引禁止などの措置を講じました。これは冷戦期の「黙認」政策からの完全な転換を示す象徴的な出来事でした。
3-2. 経済犯罪と資金洗浄の国際的取り締まり
グローバル化が進む現代経済において、国際的な組織犯罪の最大の武器は「マネー」です。2008年の世界金融危機以降、各国の金融規制当局とアメリカの情報機関は、マネーロンダリングや脱税といった経済犯罪に対する取り締まりを強化しています。
山口組を含む日本の暴力団も、こうした国際的な監視の目から逃れることはできません。特に以下の分野での活動が注目されています:
| 犯罪類型 | 具体的事例 | 関連情報機関 |
|---|---|---|
| 証券詐欺 | 仕手株操作、インサイダー取引 | FBI、SEC |
| 資金洗浄 | 不動産投資、芸能・スポーツ産業への投資 | FinCEN、財務省 |
| サイバー犯罪 | オンラインギャンブル、フィッシング詐欺 | NSA、FBI |
| 偽造品取引 | 高級ブランド品、医薬品の偽造 | ICE、DEA |
2016年、国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)が公開した「パナマ文書」には、一部のヤクザ組織がタックスヘイブンを利用して資金を隠匿していた証拠が含まれていました。こうした国際的な資金の流れは、CIA等の情報機関だけでなく、財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)による集中的な調査の対象となっています。
3-3. デジタル時代の情報戦と組織犯罪
3-3-1. サイバー犯罪と国家安全保障
デジタル技術の発展により、犯罪のあり方も大きく変化しています。21世紀の組織犯罪は、物理的な暴力よりも高度な技術を武器とするケースが増えており、山口組などの伝統的な暴力団も、こうした変化に適応を迫られています。
サイバー空間での組織犯罪の脅威
- 企業・政府機関へのサイバー攻撃
- 個人情報の窃取と闇市場での売買
- オンライン詐欺・脅迫
- 暗号通貨を利用した資金洗浄
NSA(国家安全保障局)やFBI(連邦捜査局)のサイバー部門は、こうした新しい脅威に対応するため、日本の法執行機関との協力を強化しています。特に近年は、北朝鮮のハッカー集団と日本の暴力団の間の潜在的な協力関係についての調査が進められているとされています。
しかし同時に、デジタル監視技術の発達は、山口組側にとっても対策の難しい課題となっています。かつてのように「顔役」が直接会って談判するスタイルから、暗号化された通信や複雑な組織構造を駆使して、監視の目を逃れる洗練された手法へと進化していることが指摘されています。
3-3-2. 暗号通貨と新たな資金ルート
ビットコインをはじめとする暗号通貨の登場は、国際的な資金移動のあり方を根本から変えました。送金の匿名性と国境を越えた即時取引の可能性は、組織犯罪にとって大きな武器となる可能性があります。
山口組の一部の構成員も、こうした新技術を取り入れており、以下のような用途での暗号通貨の活用が報告されています:
- みかじめ料や上納金の徴収
- 国際的な資金移動
- 違法賭博のオンライン決済
- ランサムウェア攻撃の身代金
CIAやFBIは、ブロックチェーン分析と呼ばれる技術を用いて、こうした暗号通貨の流れを追跡する能力を高めています。2020年には、日米の法執行機関が協力し、暗号通貨を用いた国際的なマネーロンダリング事件で、複数の山口組関係者を摘発することに成功しました。
このように、デジタル時代において山口組とアメリカの情報機関の関係は、かつての「政治的利害に基づく暗黙の了解」から、「ハイテク犯罪との闘い」という新たなステージに移行しています。情報技術の進化とグローバル化が進む中、この関係性は今後も変化し続けるでしょう。

4. 日米関係の裏側:外交と裏社会の微妙な均衡
表向きの日米同盟関係とは別に、両国の裏社会と情報機関の関係は複雑な様相を呈してきました。公式外交では語られない部分に焦点を当てることで、日米関係の重層的な構造が見えてきます。この構造は、しばしば政治的便宜や国家安全保障上の必要性から生まれた「微妙な均衡」の上に成り立っているのです。
4-1. 公式外交と非公式チャンネルの二重構造
戦後の日米関係において、公式の外交チャンネルと並行して、様々な「非公式チャンネル」が存在してきました。これらは政府間の正式な交渉では扱いにくい微妙な問題を処理するために機能してきたと考えられています。
日米間の非公式チャンネルの例
- 政界・財界の人脈を通じた接触
- 情報機関同士の直接的なやり取り
- 「フィクサー」と呼ばれる仲介者の活用
- 民間団体を装った情報収集活動
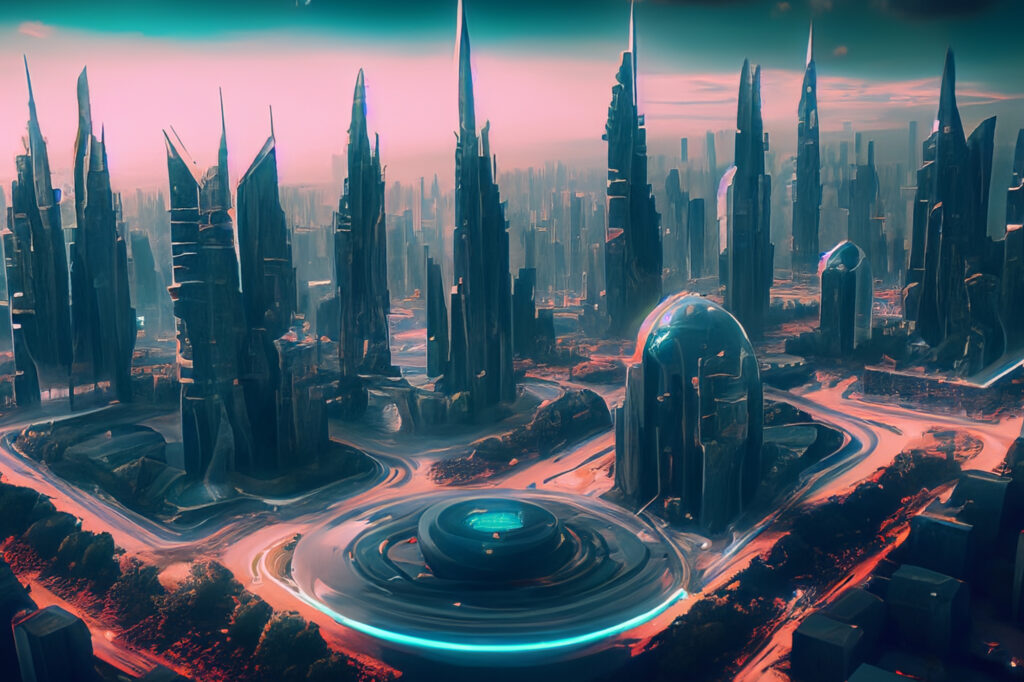
こうした二重構造の中で、山口組をはじめとする裏社会の勢力が果たしてきた役割は小さくありません。特に冷戦期には、表向きの外交では語れない「汚れ仕事」を担う存在として、一定の機能を果たしていたと考える研究者もいます。
例えば、1972年の沖縄返還交渉の裏側では、米軍基地周辺の歓楽街の管理や反基地運動への対応をめぐって、地元の暴力団と米側の非公式接触があったとされています。ジャーナリスト・ジョン・ロバーツの調査によれば、当時のCIA沖縄支部は、地元の有力暴力団を通じて情報収集を行っていたという証言が残されています。
もちろん、こうした非公式チャンネルの存在は公式には認められておらず、その詳細は今なお不明な部分が多いのが実情です。
4-2. 情報共有と司法協力の実態
冷戦終結後、特に2001年の同時多発テロ以降、日米間の情報共有と司法協力は急速に制度化・公式化されてきました。これにより、以前は「グレーゾーン」で行われていた活動の多くが、正式な協力枠組みの中に組み込まれていきます。
日米間の公式協力体制の進展
- 2004年:日米刑事共助条約の締結
- 2008年:日米情報保全協定の締結
- 2014年:サイバーセキュリティ協力の強化
- 2019年:デジタルフォレンジック共同訓練の開始
こうした公式協力の枠組みが整備されるにつれ、山口組などの暴力団に対する監視・取締りも国際的に連携して行われるようになりました。2011年に米財務省が山口組幹部を経済制裁対象に指定したのも、こうした流れの中で理解できます。
一方で、表立って語られることは少ないものの、CIAと日本の公安調査庁の間では、北朝鮮問題やアジアの国際テロ組織に関する情報交換の中で、山口組など日本の暴力団の動向も定期的に議題に上がっているとされています。特に、以下のような点が情報共有の対象になっていると見られます:
| 優先度 | 情報交換トピック | 関連機関 |
|---|---|---|
| 高 | 北朝鮮との繋がり | CIA、公安調査庁 |
| 高 | 国際資金洗浄 | FinCEN、警視庁 |
| 中 | 武器・麻薬取引 | DEA、警察庁 |
| 中 | 人身売買 | FBI、入国管理局 |
| 低 | 偽造品取引 | ICE、税関 |
4-3. 文化的相違が生む理解の齟齬
4-3-1. 組織犯罪に対する認識の違い
日米間で山口組などの暴力団組織をめぐる認識には、しばしば大きな文化的相違が見られます。この相違は、両国の情報機関や捜査機関の協力において時に障害となってきました。
日米の暴力団認識の違い
- 日本側の視点:
- 社会に「埋め込まれた」存在という認識
- 「必要悪」として一定の社会的機能を認める見方
- 表社会との境界線の曖昧さ
- 「迷惑料」「解決金」など独特の経済的関係性
- アメリカ側の視点:
- 「排除すべき犯罪組織」という明確な立場
- RICOなど組織犯罪に特化した法制度
- 「ゼロ・トレランス」の姿勢
- 経済的影響より社会的害悪を重視
この認識の違いは、例えば2015年に分裂した山口組をめぐる対応においても表れました。アメリカ側が「テロ組織」に準じる対応を求めたのに対し、日本側は「社会的混乱を避けるための管理」という姿勢を優先させたとされています。
4-3-2. 法執行アプローチの日米比較
組織犯罪対策における日米の法執行アプローチには、顕著な違いがあります。これは両国の法制度の違いだけでなく、社会的・歴史的背景の相違に根ざしています。
アメリカの法執行アプローチ
- 積極的な潜入捜査・おとり捜査
- 証人保護プログラムの活用
- 司法取引による内部崩壊誘導
- 資産没収の徹底的適用
日本の法執行アプローチ
- 監視と情報収集の重視
- 暴力団対策法による規制
- 市民参加型の排除運動
- 行政指導と経済的締め付け
これらの違いは、「山口組とCIAの関係」を考える上でも重要です。アメリカの情報機関からすれば、日本の暴力団に対する「共存」的アプローチは理解しがたいものですが、日本側の視点からは、急激な排除による社会的混乱のリスクを避けるための「現実的対応」と見なされています。
こうした認識の違いは、時に両国の情報機関の協力における「見えない壁」となってきました。しかし近年は、グローバル化する犯罪への対応として、互いのアプローチの長所を学び合う動きも見られるようになっています。

5. 未来への展望:変化する国際環境と組織犯罪の行方
急速に変化する国際環境の中で、山口組とCIAという一見すると接点の少ない二つの組織の関係性も、新たな局面を迎えています。グローバル化、デジタル化、そして国際秩序の再編といった大きな潮流は、両者の相互作用にも影響を及ぼしています。ここでは、今後予測される変化と課題、そして可能性について考察します。
5-1. グローバル化がもたらす新たな課題

国境を越えた人・モノ・カネの移動が加速する現代社会において、組織犯罪も急速にグローバル化しています。山口組をはじめとする日本の暴力団組織も、この流れから逃れることはできません。
組織犯罪のグローバル化の特徴
- 国際的なネットワークの形成と提携関係の多様化
- 多国籍構成員の増加と言語・文化的障壁の低下
- 活動領域の地理的拡大と「ボーダレス犯罪」の増加
- 国際的な金融システムの活用による資金移動
このような状況下で、CIAなどの情報機関にとっても、一国の組織犯罪を孤立した問題として扱うことは難しくなっています。特に以下のような分野では、山口組などの日本の暴力団組織とアメリカの情報機関の接点が増えると予測されています:
- 北朝鮮制裁の抜け道問題:経済制裁下の北朝鮮と密接な関係を持つとされる一部の暴力団組織の動向は、アメリカの情報機関にとって重要な監視対象です。
- 対中経済スパイ活動:米中対立が深まる中、産業スパイ活動に暴力団関係者が関与するケースが増加しているとされます。
- 国際テロファイナンス:テロ組織の資金調達ルートとして、組織犯罪ネットワークが利用されるリスクが高まっています。
- 海洋安全保障:南シナ海を含むアジア太平洋地域の緊張が高まる中、海賊行為や密輸に組織犯罪が関与するケースが注目されています。
こうした新たな課題に対応するため、アメリカの情報機関は従来の「対テロ」偏重から、より幅広い「トランスナショナル・セキュリティ・リスク」への対応へと軸足を移しつつあります。その中で、山口組などの国際的なネットワークを持つ組織犯罪グループへの監視も強化されると見られています。
5-2. 技術革新と犯罪捜査の進化
技術革新は犯罪の形態を変えると同時に、法執行機関や情報機関の捜査能力も大きく向上させています。AIやビッグデータ解析などの先端技術は、組織犯罪対策の新たな武器となっています。
技術革新がもたらす捜査手法の変化
| 技術 | 捜査への応用 | 組織犯罪への影響 |
|---|---|---|
| AI分析 | 犯罪パターンの予測、異常検知 | 従来の「カン」に頼る手法が通用しなくなる |
| ブロックチェーン解析 | 資金フローの可視化、追跡 | 匿名性のある資金移動が困難に |
| 顔認識技術 | 監視カメラ映像からの人物特定 | 公共空間での活動リスクの増大 |
| SNS分析 | 人間関係の可視化、情報収集 | デジタルOPSEC(作戦保全)の重要性増大 |
| 量子暗号 | 安全な情報共有、通信傍受の高度化 | 暗号化通信への依存が危険に |
山口組などの伝統的な暴力団組織は、こうした技術革新に対応するため、サイバーセキュリティの専門家を取り込んだり、デジタル分野での活動を強化したりする動きを見せています。一方でCIAなどの情報機関も、こうした変化に対応するため、技術部門の強化を図っています。
2019年に発覚した「山口組サイバー部門」の存在は、デジタル時代への適応を示す象徴的な事例でした。この部門は、サイバー攻撃の実行だけでなく、組織の通信セキュリティ確保やデジタル資産の保護にも関わっていたと伝えられています。
5-3. 日米協力の可能性と限界
5-3-1. 情報共有の新たなフレームワーク
近年、日米両国は組織犯罪対策における協力体制を強化しています。従来の二国間協力に加え、多国間の枠組みを活用した情報共有も活発化しています。
近年の日米協力の進展
- 2017年:日米サイバーセキュリティ対話の強化
- 2018年:デジタルフォレンジック共同訓練の実施
- 2020年:暗号通貨関連犯罪対策タスクフォースの設立
- 2023年:AIを活用した組織犯罪分析プロジェクトの開始
こうした協力の背景には、山口組など日本の暴力団と国際テロ組織や外国情報機関との潜在的な繋がりへの懸念があります。特に北朝鮮の核・ミサイル開発に関連する物資や技術の密輸、資金調達ルートとしての暴力団の役割については、日米両国の情報機関が高い関心を示しています。
しかし、こうした協力にも課題があります。日本側の法的制約(通信傍受や潜入捜査に関する制限など)や、情報共有における文化的障壁(機密区分の考え方の違いなど)が、シームレスな協力を難しくしている面もあります。
5-3-2. 市民社会と透明性の重要性

組織犯罪対策における情報機関の役割が拡大する一方で、民主主義社会における監視と透明性のバランスも重要な課題となっています。過度の監視活動や不透明な情報収集は、市民の自由や権利を侵害するリスクを伴います。
透明性確保のための取り組み
- 議会による情報活動の監視強化
- 情報公開法の適切な運用
- 独立した監視機関の設置
- 市民社会との対話・協力
山口組とCIAの関係が「陰謀論」として語られがちなのも、情報活動の不透明さに起因する部分が大きいでしょう。実際には、両者の関係は冷戦期の「暗黙の協力」から、ポスト冷戦期の「監視対象」へと変化し、現在では「国際的な法執行協力の枠組み」の中で位置づけられています。
この変化を正確に理解するためには、過去の機密文書の公開や歴史的検証作業が不可欠です。米国の情報公開法(FOIA)に基づく文書公開は進んでいますが、日本側の公文書管理や情報公開制度にはまだ課題が多いとされています。
将来的には、情報機関の活動の透明性を高めつつ、組織犯罪対策の実効性を確保するという難しいバランスの上に、新たな日米協力の形が模索されていくでしょう。そしてその中で、山口組とCIAという一見すると遠く離れた二つの組織の関係性も、より明確に理解されるようになるかもしれません。
ピックアップ記事

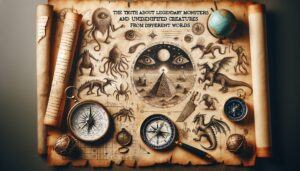

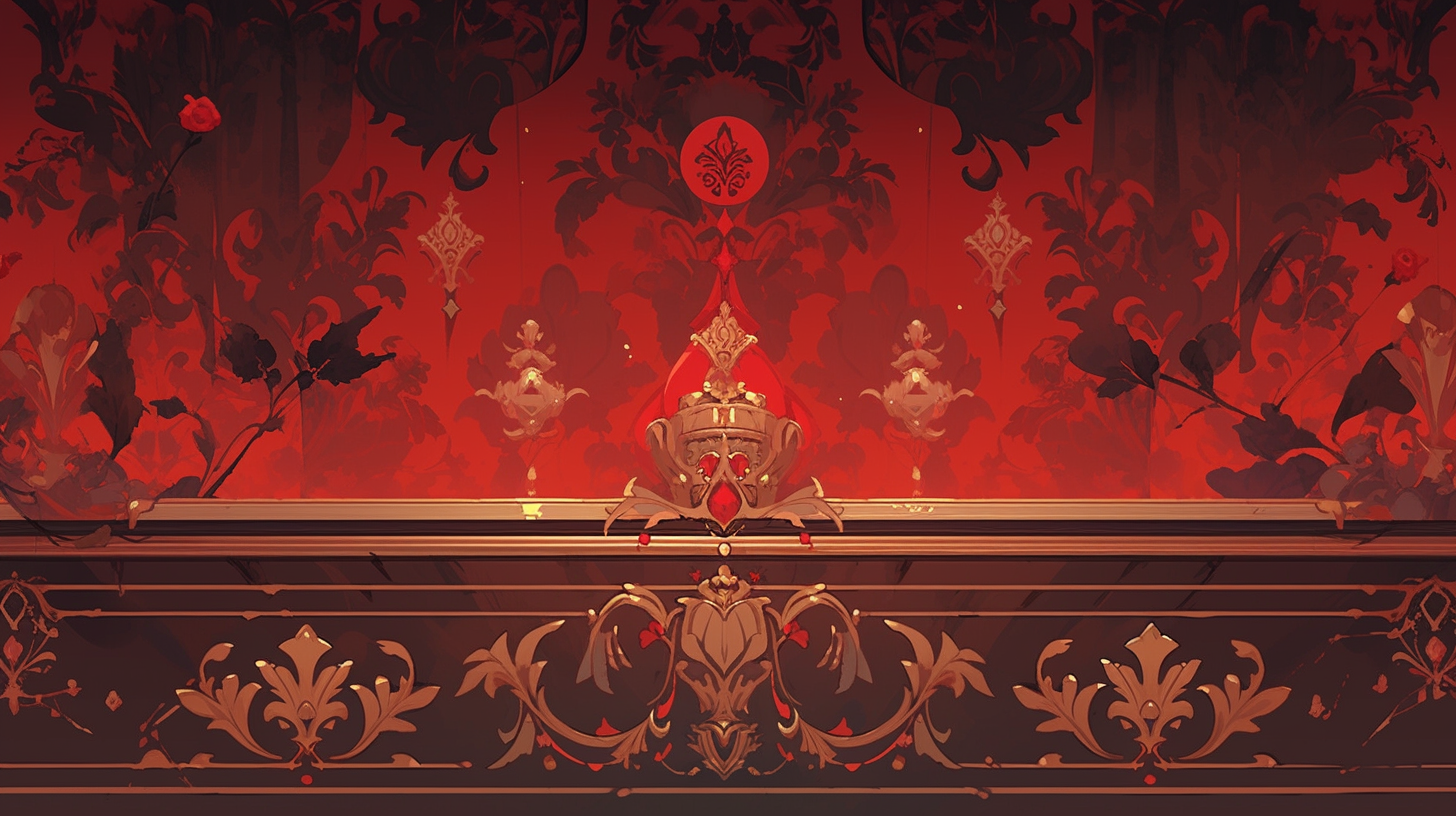

コメント